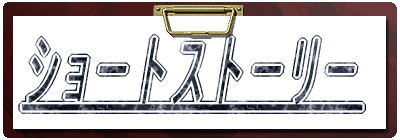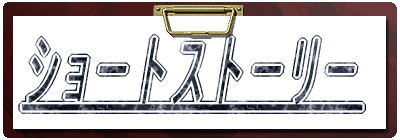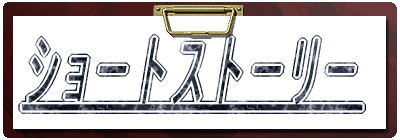
なめた時にじわじわと広がる、あの生暖かい鉄の味。サーモンピンクの舌を真っ赤に染め、その鉄臭さにもかかわらず、次を求めたくなる。
だが、血などただの副産物に過ぎない。俺が本当に求める物は……。
……傷だ。
〜 つけたがる女、なめたがる男 〜
性格ゆえに、俺は幼い頃から友達が少なかった。それでも、狭く深い関係を築けたなら、少なくとも今よりは楽しい人生を送れたかもしれない。
でも、それすら適わなかった。気がつけば、俺は常に独りだった。
「あのぉ……木戸くん……」
クラスメートの女子が一人、俺に声をかけてきた。おどおどしく振舞うが、彼女は決してそんな子ではない。相手が、俺だからだ。
「木戸くん……国語委員だよ……ね。クラス全員のノート集めたから、先生に……提出してくれる……かな」
彼女は微笑んだ。あからさまな作り笑い。顔が引きつっていた。
俺は小さく息を吐くと、そっと椅子から立った。そんな、誰もが日常的にこなす一動作を目の当たりにしただけで、彼女は体をビクつかせた。
「ありがと」
社交辞令的な感謝の言葉を口から零すと、俺は彼女が差し出していたノートの山を受け取った。ノートが手からはなれた事を確認すると、彼女は即座にいつもの派閥へ加わった。ギャル系のチャラチャラした女どもの集団が、彼女を優しく受け入れつつ、俺を白い目で見る。俺が何をした? 何もしていない。ただ椅子から立ち上がり、ノートを受け取っただけの事。ごく普通の日常的な動作だ。だが周りからしてみれば、『俺がそれをする事』が非日常的な動作だった。俺は、その存在がすでに非日常的だった。
慣れとは恐ろしい。いつの間にか、生まれたその瞬間から自分はそうだったような錯覚さえ覚えてしまう。だから、今さら周りから何をされようと、俺にとってはなんの意味もない。
俺とあいつ等には、常に壁が存在する。俺を避けるあいつ等、あいつ等の存在を特に意識しない俺。あいつ等が俺に対し、同じく俺があいつ等に対し壁を作っていた。誰も俺を必要としない代わりに、俺自身誰も必要としない。ただ、それだけの事。
暇だったから保健室で寝ていた。保健の先生に具合が悪いと言うと、それが嘘でも本当でも等しく心配し、俺をベッドで寝かせてくれた。
授業に出る気は全くなかった。勉強はわざわざしなくても生まれつき出来る人間だった。同じく運動も、とくに何をしている訳でもないのに人より出来た。それでいて、この性格、この不良ぶり。担任はさぞ手を焼いていることだろう。知ったこっちゃないけど。
どれだけ寝ただろう。時間が気になってベッドから起き上がりカーテンを引くと、そこには誰もいなかった。時間的にはまだ授業の最中のようだった。俺は小さく溜息をついて、もう一眠りしようとベッドへ戻ろうとした。
その刹那だった。保健室の戸が開き、人が入ってきた。女の子だ。
片目をなぜか白い眼帯で覆った体操着姿の彼女は、何もつけていない方の目でこっちを見て言った。
「……先生は……いないんだ」
哀しい目をしていた。不思議と感じるシンパシー。どことなく、そして何となく、匂いが同じだった。
「どうしたの? 何か怪我でも?」
そう俺が聞くと、彼女は自分の足を見た。仄かに茶色いセミロングの髪が、ふわりと揺らいだ。
「……転んだんだ」
彼女は頷いた。彼女の右足の膝には、高校生には珍しい擦り剥いたような傷跡が大きく残っていた。膿みはまだ始まってはいないが、血はやたらと派手に出ていた。その血の跡を見る限り、洗浄も消毒もしていない様だった。
「そのままにしてると、破傷風になったりして死ぬよ」
「……会ったばかりの女の子に『死ぬ』とかって単語使わないでよ」
彼女は溜息をついた。
「でも……死ねるのならこのままでも良いか」
「……自殺希望者?」
彼女は答えなかった。
「痛くはないの?」
「少なくとも、痛い痛いって喚くような歳じゃないもの」
そう言って再び傷に目を落とした。それを追う様に、もう一度俺もその傷を見る。俺の中で、どうしても抑えられない衝動がふつふつと湧き上がってきた。
俺はそっと彼女に近づきしゃがんだ。俺の目線の少し下に、彼女の傷があった。
「消毒してくれるの?」
彼女は言った。
「……似たような物かな……」
俺はそっと傷に顔を近づけ、自分の口から姿を見せている舌をその傷に当てた。
そして……舐めた。
刹那、彼女は体をビクつかせた。それは痛みによる物よりかは、むしろいきなり舐められた事による動揺のほうが大きかっただろう。
「ちょ、あんた何やって……!!」
頭を叩かれたり挙句には殴られたりもした。けど、俺はそんなのを一切無視し、彼女の血で湿った傷を、舌の先でなめた。
「痛……やめてよ!! 人呼ぶよ、変態!!」
彼女の左足から膝蹴りが飛んできた。それがちょうどこめかみを直撃し、俺は軽いめまいを起こした。だが俺は、彼女の足を掴む力を緩めず、舌を強く押し付けた。
「つ……ん――!!」
彼女の声が、ほんの少し色っぽくなり始めた。俺は今度は舌全体を使って、傷を下から上へすくい上げるようになめ回した。
「……い――痛い……から……やめ、て――」
と言いつつも、いつの間にか彼女からの抵抗は無くなっていた。俺の頭に両手を付き、痛みと、それに伴う何かを堪えるように。
彼女の喘ぎは、ますますその色を強めた。聞いているこっちも思わず勃ってしまいそうなほどの、か弱い声だった。
女の子の喘ぎ声を生で聞いたことなんてもちろんなかった。ましてや、こんな事で感じてしまうなど、今まで企画や冗談の類だと思っていた。けど、彼女は違う。俺が傷をなめるたびに、切ない声をあげ続けた。
「ん――く……」
いったん舌を離す。傷の周りの血はあらかた舐め取られていた。傷の生々しいピンク色が浮き彫りになっていた。
当の彼女は、相変わらず俺の頭に両手を付き、荒々しく息をしていた。やはり、傷を舐められ感じていたのだろう。
「……どM?」
そう呟いた刹那だった。彼女の平手打ちが俺の左頬を直撃した。これでもかと力を込めたその衝撃は、跡が残るとかそういうレベルじゃなかった。俺は軽く体を吹き飛ばされかけた。耳の奥で耳鳴りがする。
「……くっ」
あまりの突然の事に、罵る言葉すら出てこないという様子だった。今この状況で、『馬鹿』や『変態』や『キチガイ』と言う言葉はその意味すら持たない。彼女にとって、言ったからといって気持ちが楽になる事はないのだろう。無理もない。始めてあった人間に傷を舐められ、挙句の果てにはそれに対し感じてしまったと言う痴態を見せてしまったのだ。
彼女の目には、細い涙が流れていた。痴態を見せてしまったことと何も言い返せないことによる悔しさによる物なのだろうか。彼女は俺を激しく睨むと、すぐに保健室を抜け出した。
「……おもしろ……」
久しぶりに、笑った気がした。
目に眼帯をしているほどの怪我人なんだ。保健の先生が知らないはずはない。そう思ってためしに聞いてみたら、案の定先生は彼女の事を知っていた。
「久木奈々って子だけど……どうかしたの?」
「さっきの時間にここに来たんですよ。怪我の消毒をして帰っていったんですけど、眼帯をしてたから少し気になって」
先生は意味深に「ふ〜ん」と言って頷いた。
「もしかして好みのタイプとか?」
確かに彼女の顔は綺麗だった。可愛いとも思う。けど俺は違うと否定した。
「けど、なんで眼帯なんてしてるんでしょうね。物貰いかなんかかな」
俺のそのさり気ない言葉に、先生はまた意味深に「あれね……」と言った。
先生いわく、久木さんは部活動に参加していないらしい。加え自転車通学だそうだ。放課後駐輪場で待っていれば、必ず、そして否応無く出会わざるを得なくなる。俺はそう思って、放課後のホームルームが終わると、すぐさま駐輪場へ直行した。
一人の人間に、これほどまで興味を持ったのは久しぶりだった。いや、むしろ初めてじゃないだろうか。それもこれも、先生が彼女の特異な性質を教えてくれたからこそだった。
三十分ほど駐輪場で張り込んでいた頃だろうか。帰宅する生徒が極端に少なくなった頃に、彼女は駐輪場へ現れた。俺と目があった瞬間、眼帯をしていない方の目で俺を強く睨み、すぐに視線をそらした。
「冷たいな。そんなに睨むなよ」
彼女は俺を避けるように、自分の自転車へと足を運んだ。俺は彼女を追いつつ続けて言った。
「流石にあんな事をいきなりした事は悪いと思ってる。だから謝るよ。ごめん」
彼女は足を止めた。どうやら目の前の自転車が彼女の物のようだ。肩にかけていたカバンをかごへ押し込むと言った。
「本当に謝ってすむと思ってるの? 馬鹿言わないで」
醜態をさらした事による恥じらいなのかどうかは分からない。でも、彼女の言葉は所々震えていた。
「だいたい、何でついてくるの?」
「謝る為だよ」
「ならすんだんでしょ? もう帰って。目障りだわ」
「『謝る為についてきた』。だから、追いついた今この時に、また別の事をしようって思ってるんだけど……ダメかな」
彼女はすぐさま自転車の鍵をはずし跨った。そしてペダルに足をかけた。刹那俺は自転車の後方の荷台を手でしっかり掴み、彼女の行く手を後から阻んだ。
「保健の先生に聞いちゃったんだよね」
「……何を?」
「納得したよ。だからあの時感じてたんでしょ?」
「感じてなんか――」
あくまでもそれを否定する彼女に、自分自身の言葉を自分で否定させる為、俺は手を伸ばして彼女の傷に触れた。案の定、あの時と同じように体をビクつかせた。
押すだけだと痛みしか伝わらない。だから俺はその傷をそっと撫で回す。そうすれば、微かな痛みともどかしさとが合わさって最高の快楽を得られる。今までの経験から考えると、それが普通だった。
ハンドルを握る彼女の手が震える。同時に自分の足をモジモジさせた。何かに耐えているようにも見えた。
「……どうしたの? もしかして濡れてきた?」
「――違う……そんな訳ない……」
「じゃ、触ってみても――」
「――それだけはダメ!! それだけは絶対……ダメ」
やっぱりそうだ。彼女はそういう性質の持ち主だった。痛みこそが彼女にとっての快楽であり、それを求める為には自身で自分の体を傷つける事も厭わない。
「おおかたその左目の眼帯も、自分で傷をつけたせいなんでしょ?」
俺はそう言いながら、眼帯の上から瞼の辺りを眼帯ごと摩った。刹那彼女は大きく体をビクつかせ喘いだ。
「……お……お願い――だから……や、やめて――」
彼女は快楽によって潤んだ目を俺に向けて言った。けど止めたくなかった。俺は足の傷を指で刺激したまま、彼女の眼帯をはずした。
瞼に縦一線の傷ができていた。何のための傷なのかは分からない。もしかしたら、『失明』と言う最高の快楽を得たかったからなのかも知れない。傷の周りは微かに青くなっていて、少しばかり膿んでいた。ちゃんとした治療を受けていないせいだろう。
俺は少し背伸びをし、彼女の瞼を、舐めた。
「――ヒッ!!」
痛み、そして快楽。一度に襲い掛かったその快楽に、久木さんは声を漏らした。
傷はほとんど塞がっているような物だった。でも、傷にこもった熱や、膿みは、俺を十分満足させてくれた。これだから止められないのだ。傷をなめるという行為が。
やがて彼女は大きく体をビクつかせ、そして静まった。
「……どMにしてど変態。まさかそんな人間が現実にいるなんてね」
彼女は反す言葉もないのだろうか、それとも単に言葉を反せないだけなのか、沈黙を保ったまま、ただ何かに疲れたかのように肩を上下に揺らすだけだった。
「別の場所で少し話しがしたい。久木さんにすごく興味が湧いたよ」
いつだったかは忘れてしまった。もしかしたら幼い頃、自分自身のそれを舐めた事がキッカケだったのかもしれない。気がついたら俺は、血の味と傷の感触と、それを舐められる人の反応の虜になっていた。鉄臭い、錆びた味の血が舌を覆い、きっと一般人には分からないだろう、傷にめり込む糸状乳頭の感覚。「痛い」といい拒絶しながら、痛みで体を震わすそのリアクション。それだけで俺は興奮した。
だが、彼女はそれ以上の興奮を俺にもたらした。いくら変態の俺でも、AVだとかセックスだとか、そういう類の物に興味が無いわけじゃない。ただ、歪んでいるだけ。だから、傷を舐めるだけで感じ、イった彼女に、俺は非常に興味が湧いた。ただ、それだけだ。
学校の側には川が流れていた。地図に明記されているかどうかも怪しいほどの小さな川だが、その綺麗な水とそれがもたらす涼しい空気が、昔から好きだった。俺と久木さんはその土手の上に自転車を止め、川岸まで降りて河の水面を眺めた。
彼女は口を開こうとはしなかった。俺もそれに習って口を開かなかった。緊張とかそういう可愛い事のせいではない。ただ、なんとなく。さっきみたいに自分でも驚くほどのお喋りにはなれなかった。
「……変なのは……ずっと分かってた」
どれくらいの沈黙だっただろう。二人で居る事を半分忘れかけた頃に、彼女は口を開いた。
「自分でハサミとかカッターとか使って傷をつけて、その痛みを感じて、流れる血を見てゾクゾクして、そんな事が普通じゃないのは分かってた。でも……止められなかった」
「中毒ってやつだね。自傷中毒」
彼女のその中毒は、現実逃避や自己認識のためのリストカットとは、また少し違った意味合いを持つ。彼女の場合は、逃げる為でも確認の為でもなく、あくまで快楽の為。俺と同じだった。
「あなたは、セックスとオナニー、どっちを先に知った?」
いきなり何を問うのだろうと、若干引きつつ、
「セックス……か? 親父の隠し持ってたAVを初めて見て、オナニーはその後か?」
と、正直に答えてしまった。
「きっとそれが普通なんだろうな」
俺は「久木さんはどっちが先?」と聞き返した。
「……どれも後……。初めてイった時、私は自分でつけた傷を触ってた」
彼女の中毒は、ある意味で末期症状なのかもしれない。小一の頃の話しだそうだ。
「人にされた事は?」
「ある訳ないでしょ? ただでさえ、いつも独りぼっちなのに」
どこまでも俺に似ていた。人と違った性向、価値観、人間。
「……今日、初めて人にされた」
彼女は言った。
「……そして……きっともう二度と忘れられない。この痴態も、この快楽も……」
そう言うと彼女は、カバンから何かを取り出した。それは、何の変哲も飾り気もない極普通のペンケースで、彼女はそれを開き、ある物を取り出した。
カッターだ。
彼女はそれを自分の自分の左腕に軽く押し当てると、いきなり腕を引き裂いた。引き裂いた、とは言えそれほど大した傷ではない。だが、彼女の顔は痛みで微かに歪み、傷口からは赤黒い血が滴れ落ちた。
「……舐めて」
彼女は言った。
「そして私を……またイかせて……」
彼女は、自分の右手を傷口に押し当てた。刹那、微かに喘いだ。
「もう一人でするのは飽きたの……もう一人でしても……きっとイけない……。そんなの、生殺しだわ……」
俺は、自分の中で何かが大きく脈打ったのに気がついた。彼女の傷を見たから? 痛みで歪んだ顔を見たから? いや、違う。
言葉としてはまだ出て来てはいないけど、無意識の内に感じ取ったんだと思う。
「私にはもう……あなたが必要なの……」
その言葉を、無意識の内に感じ取っていたんだと思う。
「私を……必要として……」
面白い。そう、心底思った。
「だから早く……イかせて……」
こうして、俺と彼女の、歪んだ関係が、幕を開けた。
終
前のページへ