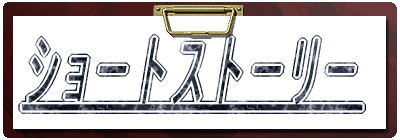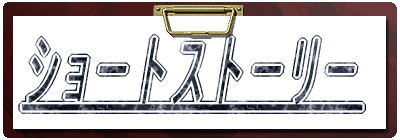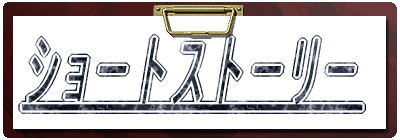
Memories Off 1st Another Story
「未来へ」
桜峰のなかでも屈指の規模を誇る、藍ヶ丘総合病院。救急救命機能を併せ持ったこの大病院の外来ロビーに、その男――鈴代康煕(すずしろこうき)は立ち尽くしていた。アメリカのバスケットボールチームの名称がプリントされている赤いTシャツと、洗いざらしたGパン。背は高く、さらにがっしりとしたその体躯の青年は、右手に携えた花束さえなければ、この病院という施設にはあまりに不釣合いであった。
康煕は、病院というところがどうにも好きにはなれなかった。絶え間なく行きかう白衣と患者、鼻につく特有の匂い。この病院の者ではないが、両親が揃って医者だというのも、彼の嫌悪感を募らせていた。先ほどから落ち着かない素振りで立ち尽くしているのは、そういった感情が先にたっているからであった。
それでも嫌悪感をおしてここまで来たのは、ある少女を見舞うためであった。
トラック運転手として働いていた康煕は3日前の雨の日、人を撥ねた。前方不注意で、赤信号に気がつかなかったのだ。あわててトラックから飛び降り、近くで立ち尽くしていた中学生を巻き込んで応急手当を施した。
やがて来た救急車にその中学生を乗せ、自分はその場に留まり、警察の到着を待った。直後、現場検証の警察官に混じって現れた刑事は、彼に3日の時間と、被害者に面会するように彼に告げたのだ。
その3日間で、康煕は身辺の整理を済ませ、会社に辞表を出し、そしてこの病院に足を向けたのであった。
だが、いつまでもそわそわしていても仕方がない。意を決し、近くを歩いていた看護師に声をかけた。
「あの……、すいません」
「は、はい!?」
「402号室……、402号室はどう行ったらいいんですか?」
声をかけられた若い、女の看護師は最初、思い切り驚いていたが、男が手にした花束を見て、笑顔を取り戻すと答えた。
「402号室ですね? あ、せっかくなのでご案内しますよ」
何か、そちらのほうに用事があるらしい。康煕はその看護師の提案を受け入れた。
エレベータに乗り、4階で降りるとしばらく歩いた先に、その病室はあった。どうやら個室らしく、容態の深刻さを物語っていた。
「ここですけど……、あの、桧月さんとは?」
どうやら、この病室の人間――桧月というらしい――との関係を尋ねているようだった。だが、「加害者です」とは言えるはずもなく、仕方なく嘘をついた。
「親類の者です」
「ああ、そうでしたか。では、私はこれで」
納得してくれたようで、看護師は軽く会釈をすると、その場から立ち去った。
看護師が廊下の角を曲がったところを確認してから、康煕は病室に足を踏み入れた。白を基調とした内装をしており、清潔感が感じられた。サイドボードには、見舞いの品が所狭しと並べられていた。ぬいぐるみや果物などの定番の品の他に、大きなヒマワリの絵があった。絵の中のヒマワリはしっかりと大きな花を咲かせていた。それが、このベッドで横たわっている者への、回復の願いがこめられた品であることは容易に予測がついた。
だが、今の康煕には絵を見ていられるような精神的余裕はなかった。
康煕は、ベッドで横たわる少女の顔を見つめた。生気の感じられない顔は陶器のように白く、今にも消え入りそうなほどであった。この少女の人生を奪ってしまったことを、康煕はいまさらながら後悔した。力なく垂れ下がった右手に手にした花束はしかし、湧き上がる悔恨の念で小刻みに震え、自身の歯軋りの音まで病室内にこだましているような感覚さえ覚えた。
俺は、どんな顔をしてこの少女に会えたものだろう。
この余命いくばくもない少女に何をしてやれるのだろう。
いくら頭で懊悩しても、今の彼にはその答えは見つからない。ならば、この少女の容態が変化する前に病室を去り、何事もなかったかのように出頭するしかない。そう思って踵を返したとき、不意に反対側からドアが開いた。
「彩ちゃーん、起きてる?」
「おい唯笑、病室でそんなでかい声出すな」
開いたドアから姿を現したのは、少年と少女の二人連れだった。二人ともベッドの少女とは友人なのだろうか、年恰好もそう変わらないように見える。
「あ、あれれ?」
唯笑と呼ばれた少女が、康煕の存在に気がついた。
「どうした唯笑? ん?」
傍らの少年も気がついた。だが、少年――三上智也が気付いたのはその存在だけではなかった。青年が手にしている花束と、少し赤くなった眼に智也は敏感に反応した。
「唯笑。ドアを閉めろ」
静かだが、力のこもった声。唯笑は智也の言い知れぬ気迫に圧倒されつつも、ドアを閉めに向かった。
智也は気がついたのだ。この男こそが、最愛の人――桧月彩花をトラックで撥ね、傷つけた張本人だということを。彼の右拳が硬く握り締められる。怨敵を目の当たりにし、智也の全身がわなわなと震えた。
唯笑がドアを閉めた。
「智ちゃん?」
心配そうな唯笑の声も今の智也には届かない。智也の憎悪は暴発寸前だった。
その様子を、康煕は驚くほど冷静に見つめていた。これから始まることも簡単に予想がついたし、何より、そうされることを自分でも望んでいたのだ。
(行けば分かるさ。それが、どんな裁判の判決よりも重たい裁きだということがな)
彼を病院に行かせた、顔なじみの刑事の台詞が脳裏によみがえる。
そうだ、俺は裁きを受けに来たのだ。あの少女を傷つけてしまったことへの贖罪は、こうすることでしか償えないのだ。
だが、康煕の思考は裂帛の叫びにより中断される。
「お前が……、お前が彩花を!!」
次の瞬間、康煕の身体は5mほど吹き飛ばされていた。康煕は殴られた衝撃で転倒し、病室の壁に背中を打ちつける。
「智ちゃん!」
唯笑が悲鳴のような叫びをあげる。だが智也はそれには構わず、倒れている康煕に馬乗りになると、両の拳で交互に顔を殴りつけた。次第に康煕の顔が腫れ上がっていく。それに連れ、自身の拳も腫れ上がっていったが、それでも智也は拳を止めなかった。今の智也には憎悪と悲しみしかなかった。殴りつけながらも瞳からとめどなく流れ落ちる涙が、言葉以上に雄弁に語っていた。
桧月彩花は意識を取り戻した。
(あれ? 私、生き返ったのかな?)
だが、そのささやかな希望もあっさり閉ざされてしまう。視線を下に向けると、ベッドに横たわる自分の姿があったのだ。すっかり顔色の白くなってしまった自身を見つめ、自分がこれから死出の旅路へ向かうのを悟ったのだった。
(そっか。私、もう死んじゃうんだ……)
ぼんやりとそんな事を考えていた彩花であったが、聞こえてきた鈍い音に耳を傾ける。そこでは恋人の三上智也が、一人の青年に馬乗りになって殴りつけていた。その横には、親友・今坂唯笑がいるのだが、彼女は顔を両手で覆い、ただ泣いているばかりだ。
殴られている青年は、あの雨の日、自分を撥ねてしまったトラックの運転手だろう。投げ捨てられた花束から、彼が見舞いに来てくれたと理解できた。そこに智也と唯笑が鉢合わせしてしまったのだ。
彩花は、肉体なき身であるにもかかわらず、振り上げられた智也の拳を止めようと両手で押さえにいった。だが、当然のように彩花の手は、智也の腕に絡むことなくすり抜けてしまう。それでも彩花は、懸命に想い人の暴走を止めようと、その腕をとろうとする。何度も、何度も。
ふと、拳が止まった。殴り疲れたのだろうか? それとも、自分の祈りが通じたのだろうか? しかし智也は、今度は青年の胸ぐらを掴んで身体を起こすと、そのままの姿勢で嗚咽を漏らしはじめた。それはやがて慟哭となり、決して広くない病室に響きわたる。
彩花は胸を締め付けられるようだった。例え様の無い悲しみが広がっていくのが分かる。それと同時に、彩花の心に一つの感情が生まれていった。
(死にたくない!)
それは、一度は手放した生への執着であった。智也の悲しむ顔を見たくない。智也が傷つくところを見たくない。彩花の願いは、愛する人の幸福に集約されていた。
もしかしたら、自分がいなくても智也はその悲しみから立ち直るかもしれない。智也の隣には唯笑がいる。唯笑も智也のことが好きなのは知っていた。そしてその気持ちが、自分がいる限り表には出さないということも。
だが、彩花は智也の恋人として、それだけは絶対に譲れなかった。智也の隣は私でなければ駄目なんだ。私が、智也を助けてあげなくてはいけないんだ!
しかし、自分はもうじき逝ってしまう。彩花は祈った。自分が天に召されるまでの間に、ありったけの思いを。生きたいという願望を。
そのとき、不意に彩花の身体に熱いものが芽生えた。その、炎にも似た力は、いわゆる幽体である彩花の全身にすさまじい勢いで流れ込んでくる。
(あ……、ああ…………)
彩花がその力に身をゆだねたと同時に、目の前の風景が全て白く消し飛んでいった。
康煕は、自分の胸に顔をうずめて嗚咽する少年を見ながら、ある結論に達したことを実感した。
自分は誰かに愛されたかったのだ。共働きの両親は仕事に忙殺され、家族のぬくもりなどは皆無に等しかった。やがて不良に身をやつし、夜な夜な喧嘩三昧。自分に付き従う者たちこそいたが、それはあくまで“舎弟”であり、“友人”ではなかった。
今、目の前で泣き崩れる少年を見て、彼は思った。
自分のために泣いてくれる人などいただろうか。
他人の痛みを自分の痛みとして、共感できる関係の人間が周りにいただろうか。
自分は人生のレールを外れ、間違った方向へ行ってしまったのだ。改めてそう思い直したとき、頭の後ろで声がした。
「智也……、もう、やめて……」
か細いが、良く通る声。康煕は傍らで泣きじゃくっている、唯笑と呼ばれた少女に視線を移す。その唯笑は絶句していた。智也と呼ばれた少年も、その声に反応し、バネ仕掛けの人形のように勢い良く頭を起こした。康煕も彼らの視線のほうに顔を向ける。そこには、まさに奇跡があった。
ベッドの上の少女が、身体を起こしていた。眼もしっかりと見開かれ、白かった顔には僅かではあるが生気の色が見て取れる。先ほどまで瀕死だった少女――桧月彩花は、涙を流す二人の友人に訴えかけた。
「お願い、もうやめて! それ以上、その人を傷つけないで!!」
絞り出すように叫んだ彩花であったが、しかし身体は、糸の切れた操り人形のように力なくくずおれる。
「彩花!」
「彩ちゃん!」
言うが早いか、智也と唯笑は彩花のもとに駆け寄る。彩花が再びベッドに倒れ掛かるあと僅かのところで、智也がしっかりと抱きとめた。もう二度と離すまいと、その腕には自然と、力が入っていた。
「大丈夫か彩花!?」
「大丈夫。起き抜けに思いっきり叫んだから、ちょっと疲れただけ」
安心させるように優しく微笑む彩花。
「本当に……、大丈夫なんだな?」
こん睡状態になってから既に3日が経過し、もはや助かるまいと思っていただけに、智也には嬉しさの反面、疑問も残った。それゆえの質問であった。
「彩ちゃん、いったいどうしたの?」
その疑問は唯笑も同じく持ったらしい。同じように、智也とは反対側から彩花に尋ねる。
「うーん、私にも良く分からないんだけど……」
そう前置きした上で、彩花は経緯を語り始めた。それは智也にとっても唯笑にとっても、また少し離れたところで聞いていた康煕にとっても、衝撃的であった。
そんな奇跡のようなことが起こり得るのだろうか?
しかし、現にこうして彩花は生きて、ここで話している。3人はそれぞれ、現実として受け止めるしかなかった。
だが、智也と唯笑にとって、そんな事はもはやどうでも良かった。死んだとさえ思っていた恋人が、親友が生きている。それだけで充分だった。
「彩花!!」
感極まった智也は、そのまま彩花に抱きついた。彩花の胸に顔をうずめながら、また涙を流す。最初は戸惑った彩花も、ゆっくりと智也を抱き寄せると、泣きじゃくる智也の頭を優しく撫でるのだった。
「大丈夫。大丈夫だから、もう……、泣かないで…………」
だが、智也が泣き止むことはなかった。恋人を失った悲しみは、幽体となった彩花も感じていたことなので、すぐには泣き止めないのは痛いほど分かっていたのだ。
ふぅ、とため息を一つついた彩花は、今度は唯笑に語りかける。
「ごめんね、唯笑ちゃん」
彩花の謝罪を、しかし唯笑は一笑に付した。
「ううん、気にしないで」
「智也の面倒見るの、大変だったでしょ?」
冗談交じりの彩花の言葉に、唯笑も笑顔で返す。唯笑というその名前の通り、笑顔がとても似合う少女。この愛らしい笑顔を見て、また一つ、彩花は自分が命を拾ったのだと実感するのだった。
「智ちゃんのこともちゃあんと見てたし、彩ちゃんがいなくても……、いなくても……」
だが、次第に唯笑の顔が曇っていく。瞳からは涙が流れ、大きく肩を震わせる。
彩花は、既に途切れ途切れになっている唯笑の言葉を手で制すると、その手で唯笑を招き寄せる。
「ごめんね、唯笑ちゃん。……ありがとう」
「彩ちゃん……、彩ちゃああん!!」
唯笑もまた、彩花に抱きついた。あまりの勢いにベッドが派手に軋んだが、そんなことはお構いなしだった。
「三人は……、いつもいっしょだよ?」
両脇に泣き続ける智也と唯笑を抱えながら、彩花は穏やかな笑顔を浮かべていた。
二人を優しく撫でながら、彩花は初めて康煕に向き直った。
「あの、あの時トラックを運転していた人ですよね?」
「あ、ああ……」
まっすぐな瞳。嘘はつけないと、康煕は即座に思った。だが、何故だか気の抜けた返事しか出来なかった。
「あの時の事、少し覚えていますよ。お兄さん、震える手で応急処置をしてくれたんですよね? あの時はもうダメかな、と思っていたんだけど、こうしていられるのはきっと、お兄さんのおかげだと思うんです。だから……、ありがとうございました」
感謝の言葉を述べ、彩花はぺこりと頭を下げた。そしてまた、彩花は智也と唯笑を優しく、優しく撫でていく。
康煕の心の奥に、温かいものが生まれるのを自分でも感じていた。両親から愛されず、気がつけば闇の中に身を投じていた康煕はしかし、荒んだ心の片隅でこんな温かさを求めていたのが分かったのだ。一緒に笑い、一緒に泣ける友人、そして環境。自分が欲して手に入らなかったものが、ここで展開されていた。それを羨ましいと感じると同時に、目の当たりに出来た嬉しさが彼の心に沁みていく。
(あ、あ? 俺……泣いて、いるのか?)
自然と涙が零れ落ちていた。自分でも驚いた康煕は袖で何度も涙を拭くが、それでも溢れる雫は止まることを知らなかった。張り詰めていたものがぷつりと切れたような感覚。次第に彼は声をあげて泣き出した。見た目、そして実年齢とのギャップを感じさせるような、子供のような泣き方であった。
そのボリュームが大きかったのか、彩花はもちろん、泣いていた智也と唯笑も驚いていた。いったい何故泣いているのか分からず、彩花と智也は顔を見合わせながら、眼を白黒させるばかりだ。
その時、唯笑は二人が思っても見ない行動に出た。
彩花の側を離れ、つと立ち上がると、顔に残った涙を強引に拭き、膝をついて泣いている康煕の前に立った。そして、背をかがめて目線を合わせると、そのままの体制で突然彼を抱きしめたのだ。
「唯笑?」
「唯笑ちゃん?」
彩花も、智也も驚いたが、一番驚いたのは当然、康煕であった。とっさのことに一瞬、身体を震わせるが、唯笑は康煕を安心させるように彼の背中をさすっていく。温かな感触と匂い、微かに、確かに聞こえる命の鼓動。ささくれ立った心を包み込む優しさ。
驚きも薄れ、安堵感の戻った康煕は、唯笑の胸の中でまた、盛大に涙を流した。そんな彼に、唯笑は優しくささやく。
「大丈夫だよ……。泣きたいときは、うんと泣かなくちゃ……」
慟哭している康煕に、唯笑の言葉は耳に入らない。ただこの温もりに浸り、泣くだけだ。それでも唯笑は、優しく言葉をつないでいく。
「お兄さんの気が済むまで、唯笑はここにいるからね……」
康煕が一生に一度、流すか分からない涙を流しきったのは、それから1時間後であった。
「それで、智也ったらヒドいんですよ! 私のこと、“口うるさいオバサン”なんて!」
「寝坊して学校に遅刻しそうになったり、授業中昼寝したくらいでガミガミ言われり あ、そうも言いたくもなるよ」
「遅刻や昼寝くらいって、それって立派にいけないことでしょぉぉっ!」
「あははははっ!」
「はっはははは!」
それからしばらく、康煕は三人の談笑の輪に入っていた。彩花と智也の“夫婦”漫才や唯笑の天然ボケなど、彼らのことを今日初めて知った康煕も、聞いていて思わず笑いがこみ上げてくるような痛快かつ明るい話だった。
話が途切れ、康煕がふと時計を見ると、既に昼の12時をまわっていた。約束があったことを思い出し、あっ、と思わず声が口をつく。
「何? どうしたの、康煕さん?」
唯笑が康煕の顔を覗き込みながら尋ねる。談笑が始まってから、三人は康煕を名前で呼ぶようになっていた。
「いや、約束を思い出してね。もう行かなくちゃ」
康煕は、表に刑事を待たせていた。その約束の時間が12時だったのだ。康煕に病院と病室の番号を教えたのもその刑事だし、時間になったら病院まで車も回してくれるとも言ってくれたのだ。さすがに長時間待たせるのはしのびない。
「どこへ?」
唯笑が行き先を尋ねようとすると、智也がそれを遮るかのように手を打った。
「それって、け……」
「あーーーーーーーーっ!!」
突然、彩花が大きな声で叫んだ。病室の窓ガラスに亀裂が入りそうなほどの大音響に、智也と唯笑、康煕は思わず耳を塞ぐ。
「何なんだよ、突然」
智也の悪態をかわすと、叫んだときの勢いそのままで唯笑に言う。
「そうだ! ねえ唯笑ちゃん、みなもちゃん呼んできてよ! 智也を連れてさ!」
「そうだねぇ! うん、いいよ!」
「ところで、何で俺まで?」
快諾する唯笑の横で、智也は疑念を持った。だが、彩花はそれを打ち消すかのような表情で智也に向き直る。笑顔ではあるが、眉間にはしわが寄り、右手は拳が力強く握られている。そして、その表情のまま、ドスの利いた声で智也に“お願い”するのだった。
「お願い、ね?」
「……わ、分かった」
こうなったときの彩花が、有無をも言わせないのは智也も知っている。大人しく従うしかなかった。
二人が病室から出て行ったのを眼で追って、完全に視界から消えたとき、彩花は康煕に深々と頭を下げた。
「ごめんなさい。ホンットにデリカシーのない子で」
「いや、いいよ。でも……、ありがとうな」
「いいえ……。あの、康煕さん?」
「何?」
「何年で、出てこられるの?」
康煕は、質問にはすぐに答えず、病室の窓から空を見上げた。夏の始まりを予感させる、どこまでも澄んだ青空。
20秒ほど間をおいて、康煕は答えた。眼はまだ、外を向いたままだ。
「さあね。でも、もう二度と君たちの前には現れないよ」
「そう……。なんだか淋しいです」
せっかく知り合えたのに、と彩花はうつむいた。
「彩花ちゃんと俺とは、被害者と加害者のままでいいんだ……」
不意に、太陽の光が眼に入った。夏の太陽は眩しく、少し痛い。思わず手で遮ってしまって気がついた。今の康煕にとって、彩花は太陽だった。長く闇の中にいた康煕にとって、その存在はあまりに眩しすぎたのだ。
「あの……」
その様子がいたたまれなくなったのか、彩花は思わず声をかけた。だが、何と言えばいいのか、言い切れないままで声になってしまう。
康煕は、そんな彩花の優しさを好ましく思った。だから、この歳の離れた可愛らしい少女を不安な気持ちにさせないよう、努めて明るく、笑顔で彩花に伝えた。
「大丈夫だよ。ムショから出たら、彩花ちゃんもびっくりするぐらいのキレイなひと女を彼女にしてやるから」
「うん……!」
彩花の顔が晴れた。その顔を見て、康煕は心置きなくこの場を去れると思った。
病室から去ろうと背を向けると、この病室に入ったときからは想像もできないほどの、自分でも違和感を覚えるほどの軽い足取りを感じた。
「じゃあな。智也や唯笑ちゃんにも、よろしく伝えてくれ」
それだけ言うと、ドアノブに手をかけた。
「康煕さん!」
その時、彩花が康煕の背中に向かって叫んだ。彼は振り向かなかった。それでも、彩花は次の言葉を叫んだ。
「本当に、ありがとうございました!」
康煕は、振り返るかわりに、手を振って応えた。
病室のドアを開けると、何故だかそこに、未来が広がっているような気がした。
「よォ」
病院のエントランスを抜けると、横から声をかけられた。
小柄で恰幅が良く、しわの深さが老練ぶりをうかがわせる初老の男。紛れもなく、康煕をここに行くよう告げた、藍ヶ丘署少年課刑事・さわまつ沢松まこと誠だった。
その後ろに、覆面パトカーと若い刑事がいた。背は高く、細身の男。いろいろな意味で、沢松と対照的だった。
「待たせたな、おやっさん」
「ああ、待ちくたびれたぜ。そのまま逃げちまうんじゃねェかと心配したよ」
そうは言っている沢松であったが、実のところは康煕を全面的に信頼していた。不良時代からの長年の付き合いで、そこは良く理解していた。
沢松は康煕の顔を見た。眼も顔も腫れ上がったその顔は、彼がしっかりと「裁き」を受けてきたことを何よりも証明していた。
「どうだい? なかなかに痛てェお裁きだったろ?」
「ああ。アンタの言った意味が、良く分かったよ」
それだけ聞けば充分だった。
「じゃ、行こうか」
沢松が康煕の背に手を回し、車に乗るよう促す。康煕は黙って従った。
車の前までくると、若い刑事が手錠を懐から取り出した。康煕は即座に両手を差し出す。だが、沢松はそれを手で制した。
「えっ?」
「沢松さん?」
沢松は制した手を康煕の両の手に置くと、何も言わずに首を振り、そのままそれを下げさせた。
そうした後で、沢松は若い刑事のほうを向くと、右の裏拳で彼の胸を小突いた。
「バカヤロ。自首してきたヤツに手錠をかけて、手柄顔するデカ刑事がいるか」
康煕は正直に驚いた。自首してきた人間にも手錠をかけると思っていたこともあるが、部下を叱った沢松のその声色は、間違いなく本気の声だった。
叱責され、うなだれる若い刑事を横目に、沢松は笑顔で康煕に言った。
「昼メシ、まだだよな? カツ丼くらい、奢ってやるよ」
「……ありがとよ、おやっさん」
沢松の提案に、康煕は腫れた顔でしっかりと笑顔を作り、答えた。不良時代の康煕を知る沢松は、彼がこういう笑顔をするのを見たことがなかったので、少し面食らったような顔をしたが、やがて照れ隠しのように、康煕の背を大きく、何度も叩くのだった。
康煕はもう一度、青い空を見上げた。その空の向こうに、何が待っているのか。まだ想像もできぬ未来に思いを馳せ、康煕はまっすぐ、力強く空を見据えるのであった。
〜終〜
あとがき
今回のお話、実は1年位前からうすらぼんやりと頭の中にあったものを、文章にして再構築したものです。ここまで時間を掛けてしまったのは、一重に自分の能力のなさを露呈する結果となってしまいましたが、ともあれ、完成できてよかった。
ちなみに主人公である鈴代康煕の名前は、中国清朝第4代皇帝(在位1661〜1722)の名前をそのまま拝借しています。
多々、至らぬところもあると思います。ですので、最後まで辛抱強く読んでいただければ、今の私にとってこれほど嬉しいことはありません。
それでは、ごきげんよう。
前のページへ