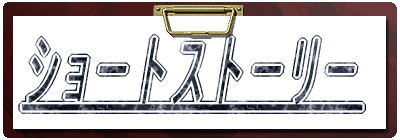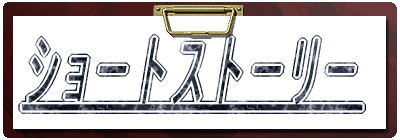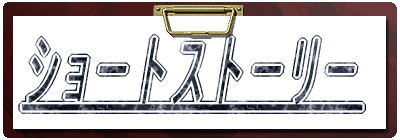
優雅に雪が舞い落ちる。
ふたりの吐く白い息は空に立ち昇り絡まり一つになり。
雪の季節が優しくうなづいた。
そして。
月の明かりを浴びて、二人のシルエットはひとつ浮かびあがった。
--------------------------------------------------------------------------------
WHITE LOVE STORY
--------------------------------------------------------------------------------
「ね、祐一。百花屋に行こうよ」
「寒いから嫌だ」
即答する祐一。
「うぅ〜。行こうよ、行こうよ」
頬を膨らませ子供のように駄々をこねる名雪。
それは水瀬家のいつもと変わらない風景だった。
「イチゴサンデー……」
名雪は上目遣いでじっと祐一を見る。
そんな名雪を見て祐一は思う。
そんな甘えた声で言われたら断れないだろ。それに今日は初めて一緒に過ごす特別な日。
けど……それを直接、口で言うのは恥ずかしいから。
祐一はさっとカーテンを開け、そっと窓を開けた。すると体の芯から冷えるような風と粉雪が入ってきた。
冷たい空気は割れるように澄んでいて。
「寒いな」
「寒いね」
二人はそう言い合うと自然に目線があって、微笑みあった。
「そうだな。……寒いし暖かいものでも食べに行くか」
そう、これが祐一流の照れ隠し。
「久しぶりのデートだね」
名雪は商店街の雪をさくさくと踏み鳴らして嬉々として言う。
「……そうだな」
百花屋に行くだけなのにデートっていうのか?
と思いつつも名雪の嬉しそうな顔を見ると祐一は恥ずかしくなって何も言えないでいた。
遠くからは教会の鐘の音と賛美歌が聞こえる。街は赤と緑と金色などの光やモールで溢れている。
通り過ぎる人々はみんな、どこか楽しそうで。嬉しそうだった。
「……ねぇ……祐一?」
「どうした?」
名雪は俯いてもじもじとしながら。
「手、つないでも良いかなぁ?」
それは空から降りそそぐ雪に溶けてしまいそうなぐらい小さな声だった。
祐一はひたっと歩くのをやめる。
少しの沈黙……。そして──
首に巻いたマフラーに口を当てて。
「寒いって言ったろ」
そう言って右手をそっと後ろに出した。
えへへ、と名雪は笑ってその手を握る。
空からは雪がゆらゆらと落ちてくる。
今日は12月24日。クリスマスイヴだった。
看板がライトアップされていて、店先にはサンタクロースに扮した売り子が出ている。
窓ガラスにはスプレーで鮮やかな色で『Merry Christmas!!』と大きく描かれていて。
その窓越しにはカップルで賑わっている。
店全体がクリスマスプレゼントに見えるかのように真っ赤なリボンで店全体が結ばれていた。
「す、凄いな」
「う……うん」
二人は百花屋の変わり様に驚き、はぁ〜、と感嘆の息をもらす。
口からもらしたその白い息は空に立ち昇り絡まりやがて一つになる。
「さて、入るか」
祐一はしあわせだった。
「うんっ」
名雪はしあわせだった。
鮮やかな緑色をしたクリスマスリースが飾られたドアに手をかける。
からんからん…
店内に来客を告げる鈴の音が鳴り響く。
「いらっしゃいま……あぁ、あなた達。久しぶりね」
「久しぶりです。席、空いてますか?」
百花屋で働いているウェイトレスの桜さん。何度もここに通ってるせいか二人は顔と名前を覚えられてしまっていた。
「えぇっと、席は……ここで良いかな」
桜はこっちこっちと手招きをする。
案内された席は窓ガラス──もとい『Merry Christmas!!』と書かれた窓ガラスの前だった。
二人掛けの白く丸いテーブルの席。
外に降る雪が見えてなかなか良い席だなと祐一は思う。
外に降る雪が見えてロマンチックで良い席だなと名雪は思う。
名雪は雪のような白のコートを、祐一は漆黒のコートを席に掛ける。
「んーと、俺は……コーヒーにしようかな。名雪はどうする?」
「イチゴサンデー、と言いたいけど……」
これ……、とメニューをつんつんと指差す。
祐一は名雪の指先を見る。
『カップル限定 ホワイトパフェ』 ──時が止まった。誰のかは言うまでもないだろう。
「ね。良いよね?」
ね、ね、と名雪は祐一に迫る。
それにたじろき祐一は赤面しながら言葉を捻りだした。
「あ、あぁ。それじゃあ……これとコーヒーお願いします」
「かしこまりました。相変わらずラブラブだね」
桜はからかうようにしてにやにやと言って、注文を届けに去っていった。
それにたじろき名雪は赤面する。
それにたじろき祐一は更に赤面する。
百花屋にはクリスマスソングが流れていた。首筋なぞるようなくすぐったい言葉で。明るく恋人達を迎えるように。
「ねーゆういち〜」
桜色に染めた顔を机に伏して甘い声で言う。
「なんだ〜?」
祐一はイスの背もたれに、もたれかかりながら答える。
「祐一の幸せってなに?」
突然の──真剣な質問。けど。
祐一はなんにも言わず、シンプルな指輪をした名雪の手にわざと、自分の指につけている同じ形をした指輪を重ねるように大きな手で覆って優しい優しい声で言った。
「名雪の本当に笑った顔見たときかな」
──じっと見つめ合う。
そうしていると急に祐一の顔が罰の悪そうな顔に変わった。
「このらぶらぶ度は天然物だね。はい、ホワイトパフェとコーヒーになります」
桜は大袈裟に腰を曲げて礼をして。
「ごゆるりと。クリスマスだしお姉さんの奢ってあげよう」
そう言ってウィンクして去っていった。
「……名雪」
「……祐一」
ちょうど狙ったように現れる桜さん。
二人は再び目を合わせる。そしてこくっと頷く。
『侮りがたし』二人は心で同じことを思う。
「けどまぁ、奢ってくれるらしいしありがたく頂きますか」
「ん。そうだね」
ホワイトパフェを目の前にして名雪の目が輝く。
その様子を見て祐一は微笑む。
二人は感じていた。
ほっとする微笑み。心にぐっとくる声。
ほっとするホットコーヒー。心にぐっとくるメロディ。
窓の外を見る。
月が昇り始める。
太陽が暮れ始める。
恋が始まる。
からんからん。
外にでると空はすっかり暗くなっていて。キラキラ輝く粉雪が舞い落ちて、それは世界を白一色に変えていた。
耳を澄ますとあんなに小さな粉雪なのに、しっかりと傘に舞い降りる音を立てている。
名雪は黙って歩き続ける祐一の手をしっかりと握りながら思っていた。
ちゃんとここに居るよって言ってるみたいだ、て。
積もった雪の上を歩いていくと、自分はここに居るんだって証みたいに足跡が残る。
あぁ、自分はこの世界に存在してるんだなって思えるんだよ。
でもたまにこう思うんだ。
やまずに降り続ける雪は折角つけた足跡も消す。
それは傷も痛みも雪と共に溶けてしまいそうで。
……それだけは絶対に嫌だ。
真実は痛いけど、逃げたくはない。
少し前までは粉雪はとても冷たいものだと思ってた。
けれど粉雪は、本当はとても暖かい。それを教えてくれたのは他ならない祐一だ。
祐一のかけてくれる言葉はとても暖かい。
恥ずかしがるけど綺麗に姿を消してくれる優しさが雪の何倍も暖かい。
『お前の本当に笑った顔見たときかな』
あの時、なんにも言えなかった。
私の笑顔を待っててくれてる人がいるって、そんなの考えたことなかったんだよ。
そう、前までは祐一のやさしさは周知のもので何も特別なものじゃなかった。
けど。
「ほら、風邪ひくぞ」
そう言って腰に手を回して暖めてくれる優しさは確かに私だけのもので。
耳に感じる吐息はとても暖かった。そしてその温もりに、祐一に、私はもう一つ教わったんだよ。
大切な事は。
幸せになりたい、という欲求より。
幸せになろう、という行動なんだって。
だから……。
「ねぇ、祐一」
「ん? なんだ?」
強く抱きしめ、首の後ろに手を回す。傘を投げ捨てた。
「名雪……」
祐一は名雪の突然の行動に驚きながらも更に強く、強く名雪を抱きしめた。
二人はお互いに見つめ合う。ふたりの吐く白い息は空に立ち昇り絡まり一つになる。
そして瞳を閉じて突き出してきた名雪の唇に祐一も自分の唇を近づけそして──。
雪の季節が優しくうなづいた。
聖なる夜にサンタが起こした結末は、
〜Fin〜
--------------------------------------------------------------------------------
あとがき
楽しんでいただけたでしょうか?クリスマスということで思いっきり甘あまなSSを書いてみました。ラストは冒頭のシーンに続くようにしてます(*^^*)
ではでは
前のページへ